現代はIT社会といえます。ITの仕組みを学びながらIT資格を目指しましょう。
本ブログで目指す資格は、「基本情報技術者試験」です。
基本情報技術者試験とは
基本情報技術者試験は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施し、「情報処理の促進に関する法律」に基づき経済産業省が認定する国家試験です。
ITエンジニアとしてキャリアをスタートする方のIT基礎力を問う試験で、「ITエンジニアの登竜門」とも呼ばれます。
「基本情報技術者試験」の試験範囲は、IPAのWebサイトに掲載されているシラバスに明記されています。
試験は、「科目A」で、知識を問う小問題と、「科目B」で、技能を問う小問題に分けて行われます。
試験は、CBT(Computer Based Testing)方式によって行われます。
そして、科目Aと科目Bの両科目で合格点を取らなければ、基本情報技術者試験の合格とはなりません。
まずは、「科目A」について、学んでいきましょう。
問題については、IPAが公開している「サンプル問題」を利用します。
この問題の取り扱いは、IPAが定める指針に基づきます。
科目A試験サンプル問題 「アルゴリズム」
問6 配列A が図2 の状態のとき,図1 の流れ図を実行すると,配列B が図3 の状態にな
った。図1 のa に入れる操作はどれか。ここで,配列A,B の要素をそれぞれ
A (i,j ) ,B (i,j ) とする。

ア B (7-i,7-j ) ← A (i,j ) イ B (7-j,i ) ← A (i,j )
ウ B (i,7-j ) ← A (i,j ) エ B ( j,7-i ) ← A (i,j )
正解:エ
アルゴリズム
アルゴリズムとは、何らかの問題を有限の時間で解くための手順です。何らかの問題をコンピューターに処理させるには、手順を与える必要があります。
この問題は、実際に値がどのように移動しているかを、適当な箇所を例にとって考えてみるとわかりやすいです。

ここで、赤丸をつけた箇所に注目します。
配列Aでは、(i,j)がそれぞれ、(0,6)となっています。
それが、配列Bでは、(i,j)がそれぞれ、(6,7)となっています。
このことから、配列Aのjの値が配列Bのiの値になっていることがわかります。
また、配列Bのj値は、配列Aの「7 – i」となっています。(7-0=7)
したがって、エ B ( j,7-i ) ← A (i,j ) が正解となります。

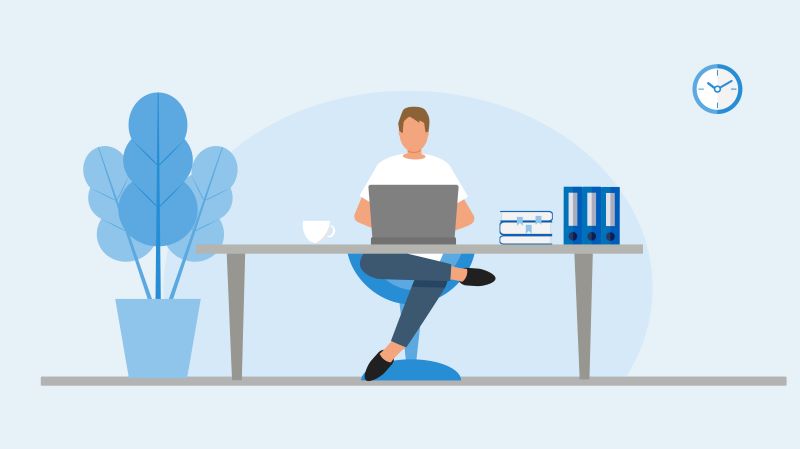


コメント